久米島紬の作業工程 糸作り
養 蚕
<桑>
カイコの餌となる日本の桑は「ヤマグワ」「カラヤマグワ」「ロソウ」のいずれかに属しています。沖縄で広く栽培されている品種は一般に「シマグワ」と呼ばれています。年間を通じて成長するので常に収穫できます。枝条が短く柔軟性があるため耐風性があり、台風などによる倒状被害も小さく、比較的栽培が楽です。
<養蚕の実際>
家蚕の卵は現在では人工孵化により餌となる桑の葉を得ることが出来れば年何回でも孵化させ飼育させることができます。孵化させるために冷蔵庫から出して、温度、光線などを調節した環境に保護することを「催青(さいせい)」とよび、11~14日で孵化します。 養蚕農家では蚕の卵2万粒入りを1単位として1箱と呼びます。
箱当たりの適正蚕座面積は一齢ではおおよそ0.2㎡ですが、五齢になると10.0から15.5㎡もの面積が必要となります。 孵化した幼虫に初めて桑の葉を与えることを「掃立」といいます。一~三齢に与える桑の柔らかい若葉は、蚕の体長と同じ大きさ位に切って食べやすいようにします。眠りの間は蚕座を乾燥させます。
蚕座は各齢期ごとに一度 は底にたまった食べ残しや糞を取り除き、清潔に保ちます。 四~五齢の蚕には新鮮な桑の葉を毎日2~3回たっぷり与えるようにします。食べ残しの葉や糞は毎日取り除いて清潔に保ちます。その場合、蚕を無闇に手で持って傷つけたり雑菌を移して病気にさせないようにします。食べ残しの桑の葉を蚕が乗ったままの状態で蚕座の脇に寄せ、中央に新しい桑の葉を置き、蚕が這って行ってそこに写るのを待ちます。
新しい葉の上に蚕が全部移動したら、食べ残しや糞を掃除し、きれいになったら蚕を葉の上に乗せたまま、また元に戻します。 五齢になっておよそ8~10日後、蚕は熟蚕となり、桑の葉を食べるのをやめ、体内の老廃物を出して小さくなり、透き通った体色になります。繭作りの準備ができたという事なので、蔟(まぶし)に移し、繭作りをさせます。
これを「上蔟(じょうぞく)」といいます。上蔟時の温度と湿度の管理が養蚕の中で最も大切なので、細心の注意を払いましょう。繭作りを初めて2昼夜ぐらいで、繭が完成します。蔟には様々な種類があります。現代では回転蔟が利用されていますが久米島ではワラの蔟が使われていました。
<選繭>
出来上がった繭は蔟からはずして選繭します。繭層が厚く、よごれていない繭は生糸用に、繭層がうすかったり、よごれているものは真綿作り用に選別します。
<繭の保存>
a.乾燥繭/繭が出来たら中の蛹が蛾になって繭に穴を開けて出てくる前に殺し、いつでも使えるように乾燥して保管します。蛹を殺すことを「殺蛹」といい、乾燥した繭を「乾繭」といいます。乾燥させることで、蛾の発生抑制、カビ発生防止、蛹の腐敗防止などの効果があります。
b.生繭/乾燥繭に対して、殺蛹処理していない、蛹が生きている繭を「生繭」といいます。以前は繭を熱処理して殺蛹しましたが、現在では冷凍処理して保存することができます。 生繭から作った絹糸は乾燥処理していないため、タンパク質が熱で変質せず、艶のある質のよい糸が出来ます。繭が少量ならば、蛾が出る前に生繭で生糸を作る方が良いでしょう。


つむぎ糸 ~真綿による糸づくり
<繭の精練>
真綿を作るためには、まず繭を重炭酸ソーダ(重曹)溶液や灰汁などの高温アルカリ溶液で精練します。繭糸に含まれるセリシンが溶けだして柔らかくなるので、真綿として引き延ばせるようになります。 繭の精練は生糸と同じように軟水で行う必要があります。精練の項を参照して下さい。
①さらしなど目の粗い木綿の白生地で、縫い代を外側にして袋を作ります。縫い代を外側にするのは煮繭した繭が布端が引っかからない為です。袋に余裕を持たせて繭を入れ、口を紐などで縛ってとめます。温湯(50~60℃)に30分ほど漬け、繭層の中まで十分に水分を浸みこませます。乾繭の場合、かちかちだった繭が触るとぺこぺことへこむようになります。上に金網などを乗せ、袋全体が水に沈むようにします。
②精練液を用意します。浴比60倍の熱湯(90℃以上)に、あらかじめ少量の水で溶いた重曹2.5g/lを加え精練液とします。重曹を加えたらすぐ繭を入れます。90℃以上を保ったままで約30分ほど煮ますが、煮ている最中はあまりぐらぐら沸騰させないように中火にしておきます。
練りむらや練りすぎがないように、5~10分おきに袋の上下を換えます。 煮繭の最中も繭を入れた袋が浮き上がらないように、上から金網などで押さえをかけます。押さえをかけるときには、袋と鍋底の間に余裕を持たせるようにして、押しつけすぎて蛹をつぶして繭を汚してしまわないように注意しましょう。袋の端などが液面から出ないように気を付けながら煮繭します。
精練が進むと繭が沈むようになります。 時々、指先で軽く触ってみて、練り具合を点検します。ペコペコとした手触りがふにゃふにゃと柔らかくなってきたら完了です。
③十分にセリシンがとれたら、軽く脱水し、常温に冷ましてから袋のまま軟水で水洗いします。手荒く扱うと袋の中で繭同士が絡み合ってしまうので、水を変えながら広げた指で優しく押し洗いしアルカリ分と不純物を十分に洗い流します。
④最後にまた袋ごと脱水します。脱水した繭は袋から出し、真綿にするまで水の中に放しておきます。


<真綿作り>
水に浮かべた繭を、1個ずつ両手の指先で表面だけ軽く包み、持つ場所を変えながらふっくらさせるように回転させると、次第に中の蛹が透けて見えるほどに広がってきます。
蚕の頭にあたる部分が一番薄くて穴が開きやすく、そこから口を開け、両手の親指を入れて少しずつ広げていきます。適当な大きさになったら内側を外側に裏返して手に被せ、繭内の蛹や分泌物を丁寧に取り除きます。繭を両手の親指と人差し指・中指を使って少しずつ四方に広げて引き伸ばします。作業はすべてぬるま湯の中で行います。
真綿はその作り方、仕上げの仕方によって角真綿や袋真綿などと名付けられます。
a.木枠による角真綿作り 引き伸ばした繭を1個ずつ耳が厚くならないように注意しながら真綿掛けにかけて正方形に伸ばします。 真綿掛けには四隅に真綿を引っかける爪が付いているので、まず並んでいる2つの爪に真綿の端をかけ、そこを起点にすると伸ばしやすいです。真綿掛けの上で引き伸ばす時は水中よりも伸ばしにくいので、 力任せに引っ張るのではなく引っ張っている方向と垂直の方向に広げたり厚くなっているところをほぐしたりしながら引き伸ばします。 全体が均一の暑さになるように引き伸ばして正方形の真綿に形作ります。慣れてくると5~7枚の繭を手に被せ、それをまとめて引き伸ばすことができます。
b.壺による袋真綿作り 手に被せた繭を重ねて30個分ほどにし、壺の口を利用して全体に引き伸ばし、袋形の真綿に形作ります。 (この方法が古いと言われています。)


<糸つむぎ(紬績)>
真綿から糸を引き出しながら指先で左右に撚りをかけるようにまとめて糸状にします。 手引きつむぎの方法は、糸に一定方向の撚りがかからないので無撚りのつむぎ糸ができます。
a.手つむぎ
真綿から糸を引き出しながら指先で左右に撚りをかけるようにまとめて糸状にします。 手引きつむぎの方法は、糸に一定方向の撚りがかからないので無撚りのつむぎ糸ができます。
1.真綿ほぐし
●角真綿
真綿の四方の重なりを均一にほぐします。 全体的に真綿を軽くはたきながらほぐし、真綿掛けの大きさに広げます。
●袋真綿
袋真綿の口の重なっている部分をほぐし、さらに袋の中に両手を入れて軽くはたき、 全体的に均一的にほぐします。
2.糸つむぎ
①ほぐした真綿を真綿掛けの針に掛け、 固定しながら上から帽子をかぶせるように全体を広げます。
②次に、真綿の中心部に穴を開けて、真綿掛けの針の外側に掛けます。
③糸口を出し、綿と糸との境目の部分を左手の親指と人差し指で押さえ、そのまま手前に引いて糸を引き出します。
④引き出した部分を右手で等間隔に3~4回よじってまとめます。 唾液を指先につけてまとめると、毛羽のない美しいつむぎ糸が出来ます。まとまったら、右手は糸を押さえたまま、また左手で糸を引き出します。これを繰り返して糸を紡いでいきます。紡いだ糸はカゴの中に落としていきます。カゴは糸が均一に積み重なるように、ときどき回転させると良いでしょう。
b.器具使用による手つむぎ
●マヌヒチャーマ利用による手つむぎ
ほぐした真綿を真綿掛けにかけて糸を引き出し、 小管に巻き取り、一方では撚りがかけられます。マヌヒチャーマを使うと、 糸つむぎ・小管巻き・撚り掛けと枠あげの工程が同時に行えます。
マヌヒチャーマのペダルを足で踏んで糸車を回転させながら、あらかじめ真綿掛け台にかけた真綿から糸を引き出し、 手つむぎと同じ要領でつむぎ、小管に巻き取ります。 巻き上がった小管は撚りを加えながら木枠に巻き取ります。 大正から戦前まで一般に久米島で利用されたものです。
●電動式手紡機による手つむぎ真綿掛けから糸を引き出し、錘を回して甘撚りをかけながらつむぐ道具です。 手つむぎと同じ要領で糸を引き出し、電動式手紡機に手で送り込みます。フライヤーが回転して撚りが軽くかかり、さらにボビンに巻き取られていきます。 久米島では昭和45年よりこの方法が利用されていました。
つむぎ糸 ~真綿による糸づくり
<煮繭(しゃけん)>
自家用の生糸は、繭を鍋で直接煮て絹糸を繰り出して作りました。はじめに原料となる繭をお湯で煮て、繭のセリシンを適当に柔らかく溶かし、 解じょを助けます。これを煮繭といいます。
煮繭が足りないと、繭から糸口が出にくく、繰糸中に糸が切れたり小節が出来たりして品質と生産の効率が下がります。 逆に煮繭が過ぎると繭層の外側が煮くずれて屑糸が多くなるだけでなく、 繰糸中に繭糸がもつれた状態でほぐれて出てしまい糸節が出来てしまったりします。
このように煮繭の工程は生糸の質に大きく影響するので生糸を作る上でもっとも重要な工程と言えます。煮繭は精錬ではないので薬品は使いません。また、硬水はセリシンの軟和を妨げる働きがあるため、 煮繭に使用する水は軟水が望ましいです。
はじめに温湯(50~60℃)に浸して繭層に水分を含ませます。元々は繭層は水に濡れにくい性質があり、いきなり熱湯に入れても煮えムラができやすいので煮繭を始める前に温湯にゆっくり浸して水分を浸透させます。 乾燥繭で20分、生繭で10~15分くらいを目安にします。
繭は水の中では浮いてしまうので、繭の上から平たい金網を落としぶたのように被わせて押さえ、 繭全体が水に浸るようにします。次に熱湯(90℃)に繭を入れて、沸騰しないように火加減を十分調節し、 7分間煮繭します。底の平らな物で繭を軽くトントンと叩いて衝撃を与えると煮繭がむらなく早く進みます。 水分が浸み込むと繭は白色から徐々に半透明がかった銀白色になってきます。これがすっかり銀色になってしまったら煮繭が過ぎてしまっています。 良い具合に煮繭した繭は、少しくすんだ銀白色で触ると表面がなめらかで押したときに弾力があります。
時々ほぐれ出て来た糸口を持ち上げてみて、煮繭の具合を見ます。 繭が繭糸に吊られて持ち上がらずスルスルと抵抗無くほぐれてくる(解じょする)ようであれば十分です。 1個の繭を持ち上げた時、たくさんの繭が一緒に上がってきてしまうのは煮繭が過ぎているという事で、ある程度糸口は出ていても一つ一つの繭はバラバラなのが丁度良い煮繭の状態です。ぬるぬるして来たら、火を止めて3分間放冷します。 湯から出すと乾いてしまうので、糸取りするまではぬるま湯に漬けておきます。
<繰糸>
糸を繰る時、上繭や玉糸の場合は座繰り操糸の方が効率よく、質の良い糸が出来ます。また琉球多蚕絹など解除の悪い繭の場合には、糸の様子をみながら繰ることが出来る手引き操糸が向いています。
煮繭したばかりの繭からは、外層がほぐれてたくさんの繭糸が互いに絡み合ってしまっています。 絡み合った繭糸の束をしばらく手でたぐっていくと、余分な糸が巻き取られ、 一つの繭からほぐれて何カ所も出ていた繭糸がそのうち一本だけになります。
糸口の出ていない繭は湯の中に入れ、緒立箒(脱穀後の稲穂を束ねたもの)をつくり繭の表面を穂先で転がすようにしてそっと撫でて糸口を捜します。稲穂が手に入らない場合は、 食器用スポンジなど、柔らかくて糸がひっかかるようなざらざらした面をもつ物で代用できます。 沖縄では伝統的にユウナの葉の裏を利用しました。
着尺経糸用生糸を作る場合、210デニールの糸を使うので3本合糸では27粒(1本70デニール)、 2本合糸では40粒(1本100デニール)、1本引きでは80粒程度(1本210デニール)を目安に常に同じ数の繭から糸が繰り出せるようにします。太い生糸をいっぺんに繰ると太さのムラや節が出やすいので、 合糸する方が美しい絹糸に仕上がります。



a.座繰り繰糸
煮繭した繭からつづみ車と座繰り器を使って糸をひきます。ケンネル撚をかけることによって、繭糸がよじれ合い、抱合するので、断面が丸く、 上質な糸ができます。久米島へは昭和6年に導入されました。
糸口を出しておいた繭を鍋に入れて目標の太さになるように必要な数の繭から糸を繰ります。 湯の温度は40~60℃位で、抵抗なく繭糸が出てくるように調節します。
追加用の糸口を出した繭の糸口をまとめ、鍋の端に準備しておきます。 繰糸している繭が薄くなったり繭糸が切れたりしたらすぐに新しい繭を追加し、また繭の外層・内層によって糸の太さが異なるので各層の糸が入り交じるように調節し常に同じ太さになるようにするのが大切です。
解じょがうまくいかない時は煮繭が足りない場合もあるので再び熱湯に戻して具合を見ながらもう少し煮ます。繭糸が切れたり薄くなって繭糸がもう出てこなくなったりした繭はこまめに取り除いて常に糸寄せの下に操糸されている繭だけのかたまりがあるようにすれば糸ムラや傷のない美しい生糸がとれます。
繭糸を追加する時は、繭糸を人差し指に掛けて手のひらに新しい繭を持ち、 繭を糸の巻き取られている繭のかたまりの中に落としてから繭糸を操糸している糸の近くに持ってゆき、そこに沿わせるようにすると自然にくっついて巻き取られていきます。繰糸を止めるとセリシンがくっついてしまうので糸を追加するときも座繰りは常に回転させたままでいるようにします。
b.手引き繰糸
座繰り繰糸と同様に、糸口を出しておいた繭を鍋に入れます。 目的の太さになるように繭をまとめ、引き出した糸を紙を敷いた広い籠の上に置きます。
右手、左手を交互に前後させて繭から糸を引きだしていきます。1個の繭から繭糸が出尽くしたときには新たに繭を補充して、いつでも同じ太さに保ちます。湿っているうちは糸のセリシン同士がくっつきやすいので、 前後・左右に糸を置いてなるべく糸同士が密着しないようにします。
解じょがうまくいかない時は煮繭が足りない場合があるので、再びお湯に戻して具合を見ながらもう少し煮ます。このような方法を久米島では「ヒッチンヂャーサー」あるいは「ずりだし」と言い、昭和の始めまで使われていました。
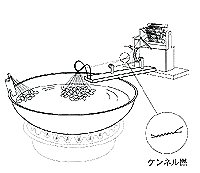
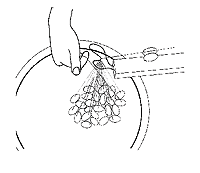
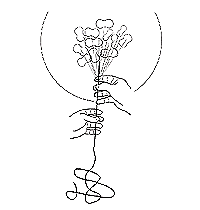
<撚糸>
生糸がバラバラにならぬように束ねて繊維を適当な太さにするために、糸に撚をかけます。手織り用の絹糸の場合、100回/m程度の撚りで十分です。200回/m以上になると仕上がりに影響が出て、せっかくの絹の風合いが失われます。
a.糸車による撚糸法(チムズン)
繰糸した生糸を小管に巻きつけます。それを糸車にセットし、糸車を3回程回転させたら小管に巻き取る方法で、撚りをかけていく方法です。特別な道具を使わない最も基本的な方法です。
b.糸車と座繰りによる撚糸法
撚糸を始める前にまず生糸を木枠から小管に巻き変えます。 座繰りで糸枠に巻き取られた生糸を、糸枠ごとぬるま湯に漬け、セリシンを柔らかくします。次に、撚糸機にかけるため、合糸する場合は2~3本の糸をまとめながら長めの管にたて巻きに巻き変えます。小管を回転させながら、縦方向にほどいて撚りをかけていくため、絹糸が出やすいようにたて巻きに巻く必要があります。
管に巻き取ったら糸が乾燥しないように水に漬けておきます。乾いてしまうと、糸に残っているセリシン同士がくっついてしまいます。 緯糸を巻くための糸車と座繰りを使って一本の糸に撚をかけることができます。
糸車に生糸をたて巻きに巻いて水に漬けておいた管をセットし、右手で糸車を回して糸に撚をかけながら左手で座繰り機を回して機枠に巻き取ってゆきます。糸車を回す速度と巻き取り速度で撚り加減を調節します。撚をかけ終わったら綛上げし乾燥させます。特別な道具を使わないで、能率的に撚りかけができる方法です。
c.簡易撚糸法(かんいねんしほう)
明治の初期に行われていた方法で、糸車を改造し、紬錘を3~5個に増やし、綛上げ機と併用して糸の撚かけを行います。 右手で糸車を回して撚をかけ、左手で綛上げ機を回して撚のかかった糸を巻き取ります。撚り数は糸車と綛上げ機の回転数の比によって決まります。
d.八丁撚糸機法
同じ原理で、紡錘(ほうすい)を増やし、糸車と綛上げ機を連動させて一定の撚加減の糸が作れるよう改良した撚糸機です。 沖縄には昭和5~6年頃熊本地方から導入され広く使用されました。右手で糸車を回すだけで撚かけと綛上げが出来ます。ここに描かれているのは10錘型で、一度に10綛の綛糸が出来ます。歯車の比によっては撚糸数を加減することができます。



<精練>
繭糸から製糸された生糸には、20~30%のにかわ状の蛋白質であるセリシンや、他の二次的な付着物を含んでいるために、手触りは堅くて光沢にも欠けています。これらを除去し、絹繊維の特性である柔らかくて光沢のある風合いを出すため、強アルカリ液で精練を行います。
精練によってセリシンや不純物の大部分を取り除くことを「本練り」と言い、精練の程度によって「三分練り」「五分練り(半練り)」「七分練り」などと言います。本練りをすると約3割近く重量が減ります。これを練り減りと言います。
a.ソーダ精練
ソーダ精練は少し硬い風合いに仕上がります。使用する水の硬度による影響が少なく、短時間に、安価で精練できるメリットがあります。マルセル石鹸と比べておよそ2倍の強い溶解力であるので、洗練のしすぎ(過精練)や練りむらが出来やすいので注意が必要です。
①前処理
ぬるま湯に浸す。または炭酸水素ナトリウム1~2%液(40℃)に10~15分漬ける。
②精練
無水炭酸ナトリウム 3~5%
無水炭酸水素ナトリウム 3~6%
中性洗剤 3%
浴比 30~50倍
温度 95~99℃
時間 20~50分
ph10.6~10.8
手で糸をつまんでみて、ぬるぬるしなくなったら完了。
③水洗い
精練の終わった糸を脱水し、冷ましてから40~50℃の温湯で、数回繰り返して洗い、さらに十分水洗いする。
最後に0.1cc/l 酢酸溶液に5分ほど浸漬して仕上げる。アルカリの中和と風合いの改良になる。
b.灰汁精練
灰汁に含まれるアルカリ分によって精練する方法です。灰はわら灰が最も良いと言われています。糸質を損なわず、美しい艶のある柔らかな光沢に仕上がります。また、植物染料の染色での発色は最良で、従来はこの方法でした。
①灰汁の作り方
糸量の2~3倍の新しいわらを短時間で焼き、黒い灰の状態でまた赤く焼けている間に、糸量の20倍程度の湯をかけて灰汁を作ります。しばらく静置して沈殿させ、上澄み液を漉し分けて精練用の灰汁とします。ph10.4になっていれば精練できます。
②前処理
ぬるま湯に浸す。
③精練
灰汁 (ph10.4)
浴比 30倍
温度 95~99℃
時間 1時間半~2時間
手で糸をつまんでみて、ぬるぬるしなくなったら完了。
④水洗い精錬の終わった糸を脱水しさましてからぬるま湯で数回繰り返して洗い、さらに十分水洗いする。最後に0.1cc/l 酢酸溶液に5分ほど浸漬して仕上げる。
経糸
●経糸用の絹糸
経糸には、生糸と玉糸が向いています。100/m 前後の撚りをかける必要があります。紬糸は経糸にして機にかけると開口の度に毛羽立ってくるので、撚りをかけるか、強い糊をつける必要があります。
経糸
●経糸用の絹糸
緯糸には生糸、玉糸、紬糸のどれもが使えます。それぞれ質感が違うので目的の風合いによって使い分けます。
